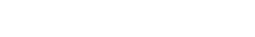【左:白川先生(理科)・右:間野先生(国語)】
【左:白川先生(理科)・右:間野先生(国語)】
海星125周年記念誌を編纂するため手に取った『海星八十五年』『海星百年』の史実本。125周年を節目に、国語科 橋本先生【海星奉職期間:昭和17(1942)年ー昭和57(1982)年】が携わった『海星八十五年』より、1945年8月9日前後の海星をブログで記しています。
本日は最終回・第三回目です。
原爆の夜
原爆の夜は火災だった。
県庁を焼き尽くした火は東へ流れ燃えひろがった。外浦町から万才町、大村町、平戸町、本博多町、新町と総なめにし、一晩中もえつづけ、紅蓮の炎は夜空を焦がし続けた。浦上の余燼(注1)も夜空を赤くしていた。長崎駅から上筑後町本蓮寺、福済寺といった大寺も燃えている。海星の丘からそうした「却火(注2)」ー原爆の火は「却火」ではなくてなんであろうかーの燃えさかる街を見おろしていると、ゴウゴウと鳴る火炎の音と、ものの崩れ落ちる響きと、そしてまっ赤な炎に照らされて、街の木も丘も空も血のような色に塗りつぶされた様子は、まさに地獄絵さながらであった。
しかも、ひっきりなしに敵機は飛来してきた。長崎における爆弾の効果に満足気な旋回をしながら、人影がチラつくと機銃掃射を浴せた。原爆の市にうごめいているのは救援の兵隊にちがいないと思ったのだろうか。それも原爆の主旨を徹底させて、生きとし生ける者は一つも残してはならぬと思ったのだろうか。とにかく、戦争というものは、人の心を残虐にするものなのだ。
悲惨な事実
川南造船所の被害は大したことでなかったので、動員の学徒たちは出動を続けた。ただ、浦上に家のあった者たちは、家は壊滅、家族の生死は不明、市内に知り合いのある者はそこを頼って行けたが、全くの浮浪者になってしまった者もいて、そんな者は学校の防空壕や教室に寝場所を求めて来たりした。
間野先生の嬢さんは県立高女の生徒だったので、女子挺身隊として三菱兵器製作所に出動してた。兵器にいた者はほとんど全滅だと聞いた先生は、そんなら、せめて遺体でも探しに出かけたのであるが、なにしろ原爆の却火は道を塞いでしまっていて浦上地区にはまるっきり近づけないのである。そこで西山水源地の上へ登り、金比羅山の裏側の山道や畑のあぜ道をたどって、やっと三菱兵器のあったあたりに出た。
その道に、先生の心を暗くしたのは、山道やあせ道の道端に、うずくまったり、転がったりしている数え切れないほどの人々の姿であった。すでに呼吸していないらしいもの。うめき声だけをもらして、意識はないらしいもの。「水、水」と細い小さな声をやっとしぼり出しているもの。その間を通りながら、先生は気が遠くなりそうだった。やっとたどりついた兵器製作所は、門も塀も崩れてしまっていたが、もちろん、うごめいている人影などはどこにも見当たらず、また中へ踏み込むことも出来なかった。歩けるところを歩き、元気な人に声をかけて見るのだが、その人たちも身内の者を探しに来てる人たちで、反対に問い返されるありさま-。
「先生、間野先生」
うろうろしていると「先生、間野先生」と呼びかけられ、見ると、道端にボロボロの学生服の若者がしゃがみこんでいた。顔をのぞきこむと、三年ほど前に海星を卒業して医専に入学した野口という青年だった。水を飲みたいのだが、足が動かない。水を頼みますという。先生は、用意して来ていた水筒の水を飲ませてやり、「若い者が、そんなことでどうする。元気を出せ。今に救護班のものが来るからな。」そう言い残して、娘さんを探し続けたのであった。
けれども、とうとう娘さんには会えず、もしかしたら、家に帰っているかも知れないと、そうなっていることを祈りながら帰ったのであったが、その夜、深更にころになって、ひょっこり、娘さんは独りで帰って来た。放心状態で、何をたずねてもはっきりした返事はせず、ただ金比羅山の木立の間を、さんざん歩き回って、やっと家にたどり着いたのだと言い、すぐに寝てしまった。かすり傷一つなかったので、まあよかったと喜んだのであったが、翌日から、原爆症状がはっきりと現れはじめ、中一日おいて、呼吸しなくなってしまった。才媛で最愛の末娘だった。
愛する人たちの行方
竹内先生も間野先生も同じ道をたどって浦上入りをした。奥さんを西町の丘の上にある真宗寺に里帰りさせていたのだった。寺のまわりは畑と墓地と藪ばかりだったから、絶対に安全と思われていたのであった。寺は壊れてしまっていたが、和尚さんたちは無事だった。ところが先生の奥さんだけは、ちょうどその刻、庭に出ていて、まともに閃光を浴び、数十メートルの崖下へ吹っとばされ、即死だった。
川上校長も浦上在住のだれかの安否を気づかって、これは風上の方の稲佐山麓を回って竹の久保から城山へ出た。そこで海星の事務室に勤務していた斉藤淑子が、ただ独りボンヤリと崩壊した家の庭に立っているのに会った。家族は全員爆死らしかった。長崎には他に行くところもないというので、学校へ連れてきたのだった。間野先生の嬢ちゃんと同じ高女卒業の、在学中から才媛の誉れが高かったのであるが、やはり同じ原爆症状が顕著で、校長の手厚い看護のかいもなく、間野先生の嬢ちゃんと同じ日に瞑目した。学校の先生たちは、警察の指示に従って建物疎開趾の空地でダビにふした。
街の余燼もおさまったころ、県庁から司令があって、学校にある御真影の奉安所を愛宕山頂に設けたから、ただちに奉納するようにとのことであった。その日の夕方、薄暑のころ、私が先導し校長が奉持して愛宕山に登った。山頂には神社があり、その拝殿のはじとみの中にはローソクの光がほのかな輪をつくっており、その奥が岩むろになっっている。そこが奉安所になっていた。市内の校長たち数名ずつ交替で「とのい(注3)」することになっているそうである。(終戦後、御真影はそこから直接、県庁へ納められたのであった。)
白川先生
白川先生は中町教会の近くに下宿していたのだったが、原爆の夜の火災で全焼してしまったので、宿がなくなり、止むを得ず、学校の理科標本室の散乱したものを整理掃除して、そこで寝起きしていた。蚊がものすごくて閉口したそうである。先生と同じように、寝場所を失った海星の生徒が頼ってくると、先生は自分の寝台を提供していた。
原爆症のものが来ると、先生はその看護もした。おかゆを作って食べさせたりしたが、そのかいもなく、空しくなったりすると、ダビにふし、その遺骨の安置場所を遺族の人に通知する世話までしたのである。家庭的学校をモットーとする海星の、職員と生徒との間に満ちている温情が、遺憾なく発揮されたのであった。
 【原爆焼け跡での慰霊ミサ・海星100年記念誌より】
【原爆焼け跡での慰霊ミサ・海星100年記念誌より】
※文は『海星八十五年史』原文のまま。
※注1「余燼」(よじん)・・・まだくすぶっている火。
注2「劫火」(ごうか)・・・仏教で、全世界を焼き尽くすという大火。この世の終わりかと思わせるほどの大火。
注3「とのい」・・・古代日本の職掌で「宿直(とのい)」と書く。宮中・役所に泊まり一晩中警備警戒すること。
8月15日・終戦の日
橋本先生が中心となって記した『海星八十五年』には、原爆から数日経ち無残で悲惨な海星ブログには書くのを躊躇するような現状が明記され、そのような中、8月15日を迎えた長崎の様子も記しています。
ーそんな長崎が迎えた「終戦」の日なのだ。「敗戦」の悲しみだの、「終戦」の安堵感だのといったものよりは遙かに深刻なものが、だれの胸にも流れていた。
しかし驚くべきことに海星は9月1日に、第二学期・始業式を迎え学校が始まっています。七月在籍数の五十八%がかろうじて登校。
混乱の中、英語科・江口実先生は通訳官になるために退職。さらに学校から、教練科(体操科の兵式体操)がなくなり、武道も学校から追放。(後になって、運動競技の一つとして放課後に希望者だけなら練習してもよいということになった。)このため教練科の先生は退職。武道の先生は、原爆の被害修復や物凄い食糧難になることが明白だったので、畑作業の重大な仕事を受け持つため、作業科の受け持ちとして残ったそうである。
海星八十五年
三回に分けて海星ブログに今回記す機会を得た1945年8月9日前後の長崎。そして海星の様子。第1回を読んだという卒業生からは「母校」を通じて戦争の恐ろしさ、平和の尊さを感じたと、有り難くわざわざ連絡をもらった。
最後に『海星八十五年』記載の1カットの写真と、その横に記してある橋本先生の言葉を紹介してシリーズを終える。
 【昭和の初めから海星卒業アルバムには卒業学年のグループ写真が掲載されていた】
【昭和の初めから海星卒業アルバムには卒業学年のグループ写真が掲載されていた】
橋本先生は、昭和五十七(1982)年まで海星に奉職した。
日本の、長崎の、そして海星の驚くべき復興力を同じ時代に体感し、またその一翼を力強く担われ、後世に伝える使命感を得ながら『海星八十五年』を担当し、教壇を降りた。
明日は8月9日。
※写真は、海星八十五年・卒業アルバムより。