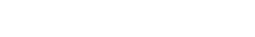【左:海星八十五年史担当・橋本先生(国語科)・右:海星第13代野口校長先生】
【左:海星八十五年史担当・橋本先生(国語科)・右:海星第13代野口校長先生】
今朝は朝焼けのグラデュエーションがとても綺麗でした。朝方頭上には煌々と月が輝き、その周囲には輝きを放つ夏の星々。早起きをすると、いつもとは違う光景に出会います。
猛暑が続く今夏ですが、朝風にそよぐ草木を見ると次の季節を探し視覚だけでも涼を求める夏の朝。にわかには信じがたいかもしれませんが、来週火曜日からは立秋です。73年前の夏はどんな朝だったのか。
今日の海星ブログは、昨日更新(再掲)の続きです。
史書 海星八十五年より
1945年6月には海星学園が機銃掃射を受けるほど、制空権を失っていた現状。8月1日には長崎医大付病院までもが爆撃される。戦争の惨さ。
国語科・橋本国廣先生【国語・漢 昭和17(1942)年ー昭和57(1982)年】が記した海星記念誌より、1945年8月9日の様子を3回に分けて平成の海星ブログに綴ります。本日は第2回。
本日は前回の最後部分から。『海星八十五年』より、以下原文のまま。
1945年8月9日 午前11時2分
学校ではその十一時、川上校長とわたしとは校庭の地下壕の御真影奉安所の前にいた。帯剣銃装した奉護の四年生、二人が同席していた。教練の「助教」として毎日二人ずつ交替で来ていたのである。川上校長が、「十一時を過ぎたから、校内を一巡してくるよ。」といって壕を出て行って、一分とはたたなかったろう、もの凄い爆発音と震動、爆風が壕内を襲ったのは-。わたしたちは顔を見合わせた。
爆弾だ、すぐ近くに、相当大きいぞ。どの顔もそう言いたげだった。校長の安否が気になった。しばらくたって、二年生が一人、駆け込んできた。
「浦上が燃えよります。ものすごい煙です。」
ひどく興奮している。そこへ校長が戻って来た。顔面蒼白、腕に幾か所も血をにじませている。理化学館の入り口のガラス戸を開けた途端、ピカリと来、ドスン、バリバリとガラスが砕け飛び散った。校長は壁にからだをたたきつけられたそうである。腕には無数のガラスの破片が突きささっていた。
その時の海星
化学実験室には科学担当の白川乕市先生がいた。茶色をした岩塩を精製していたのであるが、見事な純白の食塩ができたので、その出来栄えを、窓の外にいる伊藤先生に見せようと一歩踏み出したとき、ピカリ、ズドンと来た。窓の外を見ると、黄色みを帯びた茶色の大きな火の玉が、数十メートル離れた民家の屋根あたりに落ちたーと同時に、ものすごい爆風に襲われ、思わず座り込んでしまった。そこに校長先生が姿を見せた。
窓の外の伊藤先生は、校庭の菜園にいた。栽培してあるトマトをちょうど食べごろなのを収穫していたのであった。閃光も、爆音も白川先生と同じものを見、聞き、自分では地面にからだを伏せたつもりだったのに、からだはフワリと宙に浮き、近くの溝の中へドシンと落とされたのであった。
 【上グラウンド周辺は、戦時中菜園だった。ー昭和16(1941)年 海星卒業アルバムより】
【上グラウンド周辺は、戦時中菜園だった。ー昭和16(1941)年 海星卒業アルバムより】
「私がいた位置は、校舎の影だったので原爆の閃光を直接には受けなかった。それで助かったのですよ。」先生はそう述懐している。
会計の末吉好門先生は、その時刻、ちょうど会計室にいて、だれかに、新しく出来たばかりの二十円札を召せていた。最初にピカリときたとき、思わず窓の外を見ると、黄色やオレンジ色の火の箭が、まるで夕立の雨足のように降りそそぎ、それが火の玉となったーと同時にズシン、バリバリと爆音、爆震、爆風が一つになって襲いかかり、机の陰に伏せてしまった。
竹内先生は、会計室の廊下で爆風に足をさらわれて、身体が宙に浮き、廊下の床にたたきつけられた。職員室の前に幾人かの生徒がいた。それが、「竹内先生が死んだ」と叫ぶのを聞いた。あとでカンカン帽子をかむっていたことを思い出し、そこらじゃうを探したが、どこへふっ飛んでいったのか、とうとう見つからなかった。
ポストラにいた久松浅右エ門先生は、その夜、川南へ出かけることになっていたので、二階の部屋の蚊帳の中で熟睡していた。何か異様な感じがして、目をさましてみると、階下の廊下に蚊帳にくるまって寝ていた。「だれが、こんな所へ移したのか」そうつぶやきながら起き上がったのであった。
原爆直後の長崎は
十二時近く、わたしは初めて校庭に出て見た。出て見て、あたりの風景が、ー長崎の街も港も、稲佐の山並み鍋冠山も、愛宕山も彦山も、そして天空も、とにかく、天地のすべてが異様な真昼の静けさなのに気付いた。
一口にいって、それは「水底のような静けさ」とでもいえそうだった。
もののすべてがー色も光りも姿も、ドロンと淀んでいるのだ。「何という静かな、しめった空気だろう」-。ただ、浦上だけは・・・これはまた、何という物すごさ。黒煙、白煙入りまじり、時にはメラメラと燃えたつ炎もまじえながら、浦上の上空を覆い尽くしている。これは淀んでいない・・・バクバク、モウモウと渦巻き、逆巻き、立ち昇り、東へ東へと流れていく。海星から見ると、竹の久保、城山あたりが煙の西の極限で、まるで天地の間に踏みはだかり、むくむくともりあがる真黒な大魔王が、東へなびき流れて金比羅山に襲いかかり、山を押しつぶそうと力んでいるように見えた。
あの大魔王のせいだな、長崎の静けさは-? そう思った。全く、街も山も、空までが、シィーンとかたずをのみ、呼吸を殺して、ことのなりゆきを見守っている。そう感じた。
校舎内は
教室を見て回った。窓ガラスはほとんど砕け飛びちっていたが、不気味なほど完全に無事な窓もあった。博物標本室がひどかった。松島先生自慢だった世界的という標本類。蝶の標本棚がもろに倒れてしまって、散乱した美しい羽とガラスの破片が入りまじり、万花鏡のようだった。アルコール漬けの魚類の標本ビンも、剥製の鳥類も、植物標本の紙の束も、崩れ壊れ飛び散っていた。
 【標本室と松島先生ー同海星卒業アルバムより】
【標本室と松島先生ー同海星卒業アルバムより】
菊池幽芳が毎日新聞紙上で激賞していた南洋王の蒐集品も飾棚ごと倒れてしまった。校舎は、旧レンガ造の本館も、木造二階建の新校舎も、どちらも窓のガラス戸を修繕すれば、どうにか授業するのには支障なさそうであった。不幸中の幸いであった。
午後一時過ぎ、学校に残っていた先生達と校庭へ出た。浦上の物すごさと、街の静けさとは相変わらずだった。ただ、県庁の建物の中央あたりから、まるで線香の煙のような一筋の細々とした白煙が、静かにーたった一筋だけ、しまも真直ぐに天空に向かって立ち上っていた。それは天空と県庁との間に引かれた一本の細い白い煙の直線であった。だが、それは、やがて四時ごろになると、もう線香の煙ではなくなっていた。モクモクと勢いづいて立ちのぼり、しかも数か所に増えていた。県庁もこうなっては手がつけられんでしょうなと先生たちは話し合った。
海星 楠の樹
海星の校庭にある大きなくすの木は、原爆の直後に見たときは何の変化もなかった。ところが翌日になると、浦上の方に面した葉が薄く焦げた色になっていた。家の障子の紙もそうであった。当日はなんともなかったが翌日になると焦げ茶色に変り、まさに発火寸前のありまさだった。
浦上全滅
香焼造船所から見た原爆きのこ雲は物すごかった。野口先生は生徒たちの作業場を一巡して、教官控室に戻ってきたところであった。閃光と爆音と爆風とはやはり強烈だった。二階の教官室から防空壕へ避難しようとして、階段を滑り落ちた人もいた。帰る時間になって生徒の点呼をとり、波止場の桟橋へ行ってみると、ちょうど長崎から船が着いたところだった。甲板に、まっ白にからだ中に繃帯を巻いた人がうずくまっていた。しゃがみこんだまま動かないでいる。それは古事記の中の、あの大怪我をした因幡の白兎を思わせた。
「ひどか爆弾ですばい」
「浦上は全滅しとります」
そんな話し声を聞いても野口先生はまだ半信半疑だった。先生の生家は高尾町だったのである。浦上とはいっても山手の方だったから大丈夫だろうー強いてそう思っていた。(けれども、実際には、七人の肉親が被爆死していたのであった。)
原爆の夜は火災だった。
※文は海星八十五年史原文のまま。続きは明日更新します。
 【海星中央館から浦上方面を望む】
【海星中央館から浦上方面を望む】
爆弾だ、すぐ近くに、相当大きいぞ。どの顔もそう言いたげだった。校長の安否が気になった。しばらくたって、二年生が一人、駆け込んできた。
「浦上が燃えよります。ものすごい煙です。」