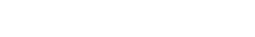おはようございます。本日は10月29日(水曜)、今朝の気温は11℃、朝5時段階で体感温度は6℃です。澄んだ空気が頬を刺す朝となりました。二十四節気では、23日(木曜)の「霜降」を過ぎ、秋も終わりへと向かう頃です。

そして、明日はいよいよ高校の学園祭。放課後からは設営やリハーサルが本格的に始まります。朝夕の冷え込みが増す一方で、校内はどのクラスも熱気に満ちています。すでにInstagramでも準備の様子が投稿されていますが、授業で訪れるたび、装飾が少しずつ施されていく様子に、明日への期待が高まります。今日の放課後には、教室の雰囲気が一気に“祭り”へと変わる瞬間が見られることでしょう。
さて、昨日の出来事をひとつ。中央館2階から外に出て、自販機のあるピロティを抜けて中学校舎へと向かう階段の脇で、ふと目をひく光景に出会いました。
枝先に実る、陽に照らされた「柿」です。

まるで太陽を閉じ込めたような照柿色(てりがきいろ)。晩秋の10月にふさわしいその輝きに足を止め、個人的に好きな俳人の一人、正岡子規の「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」の一句が自然と浮かびました。子規の句には「柿」を詠んだ歌が多く、五感をフル活用させてくれます。赤みを帯びた橙色…江戸時代の染色書には、赤土で染めた布を“照柿色”と呼んだと記されています。艶やかに実る柿の色に、季節の深まりを実感できた日でした。
そして、学園祭の翌々日、11月1日(土曜)は創立記念日です。
本校では、この日に「学園慰霊ミサ」を行います。
全校で聖歌を練習できるのは、慰霊ミサを前日に控えたリハーサルの一度きり。そこで、今週からお昼の校内放送で聖歌を流す試みが始まりました。


(※7月に有志の生徒たちの歌声を録音した様子)
今回はその収録に参加した男子生徒4人に取材することができました。
もともと歌うことが好きな彼ら。放送で自分の声を耳にしたとき、「あっ、自分の声かも?」と思ったそうですが、「女子の声がよく通っていて、自分ももっと声を張ればよかった」と少し照れ笑い。

好きな聖歌を尋ねると、
「めぐみのみ母よ」は深くゆったりとした低音で歌いやすいと話してくれました。また、「地の上のどこにも」は閉祭の歌として明るい希望を感じる曲で、「歌詞がとても好き」と語ってくれました。取材のあと、マリアン聖堂で「めぐみのみ母よ」をアカペラで披露してくれ、その清らかな響きが聖堂内に広がりました。

「また機会があればぜひ歌いたいです」と笑顔で語ってくれた姿が印象的でした。
今回の「聖歌放送の試み」の提案を受けたことで、収録に立ち会った芸術(音楽)科の浦川先生にも、当時の様子を伺いました。
「7月に有志の皆さんで聖歌の録音を行いました。録音後にはおやつを食べながら楽しく交流もできて楽しいひと時を過ごしました。全校で聖歌を練習する機会は少ないので、昼休みにこの音源を流すことで、少しでも聖歌に親しんでもらえればと思います。慰霊ミサでは『いつくしみふかき』『神ともにいまして』『めぐみのみ母よ』『地の上のどこにも』の4曲を歌います。聖歌は祈りです。厳粛なミサの中で、元気な歌声が祈りを届けてくれることを期待しています。」

放課後の熱気と、聖堂に響く静かな祈りの声。
たたかいのおともない やわらぎの日の来るために
ひととひとたすけあう せかいへいわの来るために
老いしひとかんしゃする まことのせかい来るために 「閉祭の歌:地の上のどこにも(一節)」
季節が照柿色に染まる今、学園の一日一日が確かな輝きを放っています。
※写真は、下グラウンドから伸びる柿の木、学園祭準備風景、聖歌収録に参加した有志生徒の様子